今年の配当金の大筋がわかったので考察しました。
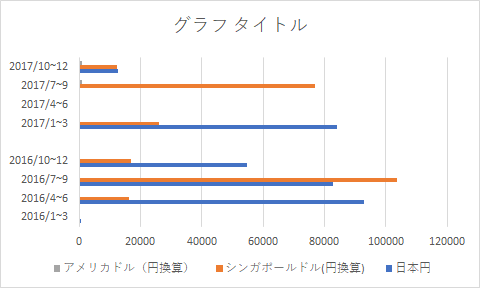
今年の配当金の累積は214358円でした。
昨年と比べると配当が少ないのですが、これの理由は配当目的の
株式取得をやめたからです。
現在は超長期保有なので、今年のほうが純粋な配当です。
シンガポール株の大幅含み損がありますが、
同時に含み益のある株もありますので、含み損益は除きますと、
ここに貸株金利が少々加わりますので、
約2%の運用益ということになります。
株価続伸の今年の世相からはとても、
結果が良いとは言えません。
なぜ結果がこうなったのか、真摯に考察して来年に生かしたいと思います。
原因
1、配当性向の低い銘柄の投資が年初めに固まった
2、配当月の異なる銘柄に分散していなかった
3、値下がり銘柄をドルコスト平均法で緩和を試みたため
4、インフラ系でも続落して選択ミスが思われる
5、海外株式の運用コストを甘く見た
これらが折り重なったことで、
現在の投資額に見合わない低い運用率になったものと思われます。
実際、iDeCoに運用させている銘柄は
3~10%の運用益です。
銘柄の変更にはほとんど手数料がかかりません。
やはり長期運用に関する下調べが不足していことから、
場当たり的な運用になっている恐れが示唆されます。
来年に関する方針
来年に関しては、もっと確固とした方針で臨む必要があります。
超長期戦略を基本として、
米国インフラ株の買い時と現在値を広く検索しておく
現在所有が膨らんでいる、ドルコスト平均法に関しては、
高配当ものに関しては、買い足しても構わない(?%を目安にする)
日本株に関しては、高配当が望めないうえに下落リスクが高いので、
早期に手放す。
現在のシャープも続伸後、伸び悩んでいます。
配当もなく、貸株金利 0.75% のみです。
もちろん普通預金よりいいのですが、リスクが上回ります。
さて、外国株の買い足しですが、どうするのが良いのでしょうか?
適切な%をご存知でしたら教えてもらいたいです。
では